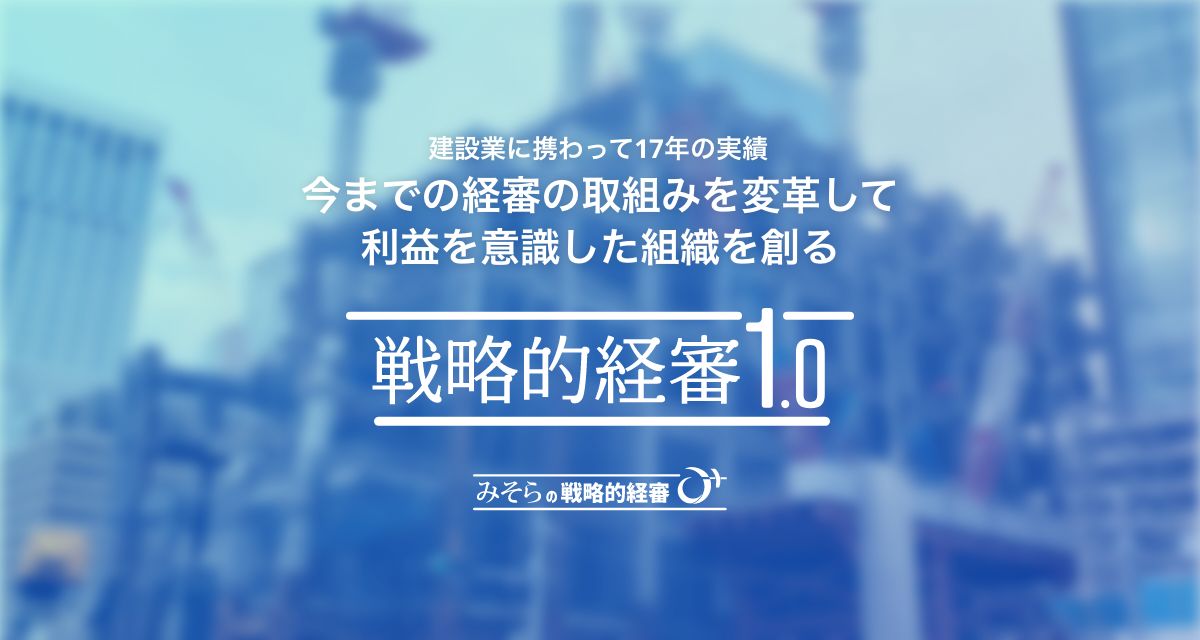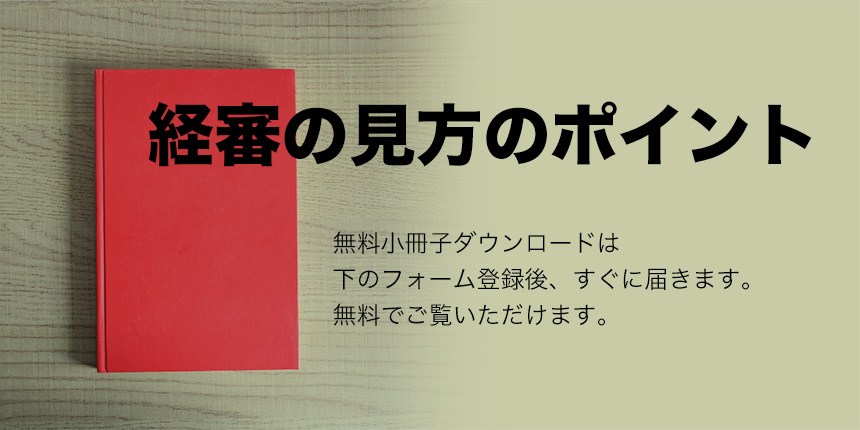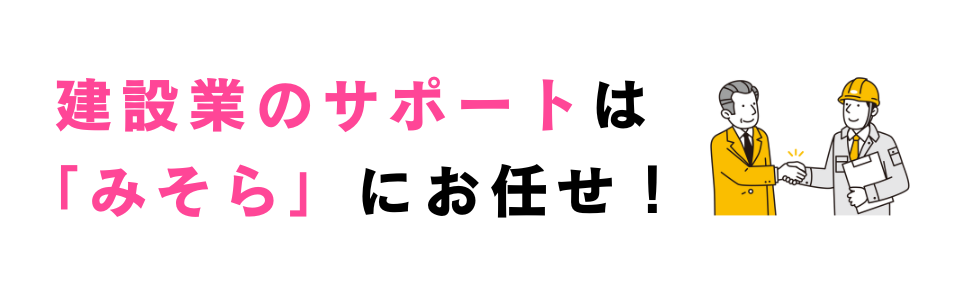

「経審の点数をより良くしたい…!」
「経審の点数を最適化して公共工事をより良い条件で受注したい…!」
無料ダウンロード 経審の見かたのポイントはこちらからダウンロードいただけます。
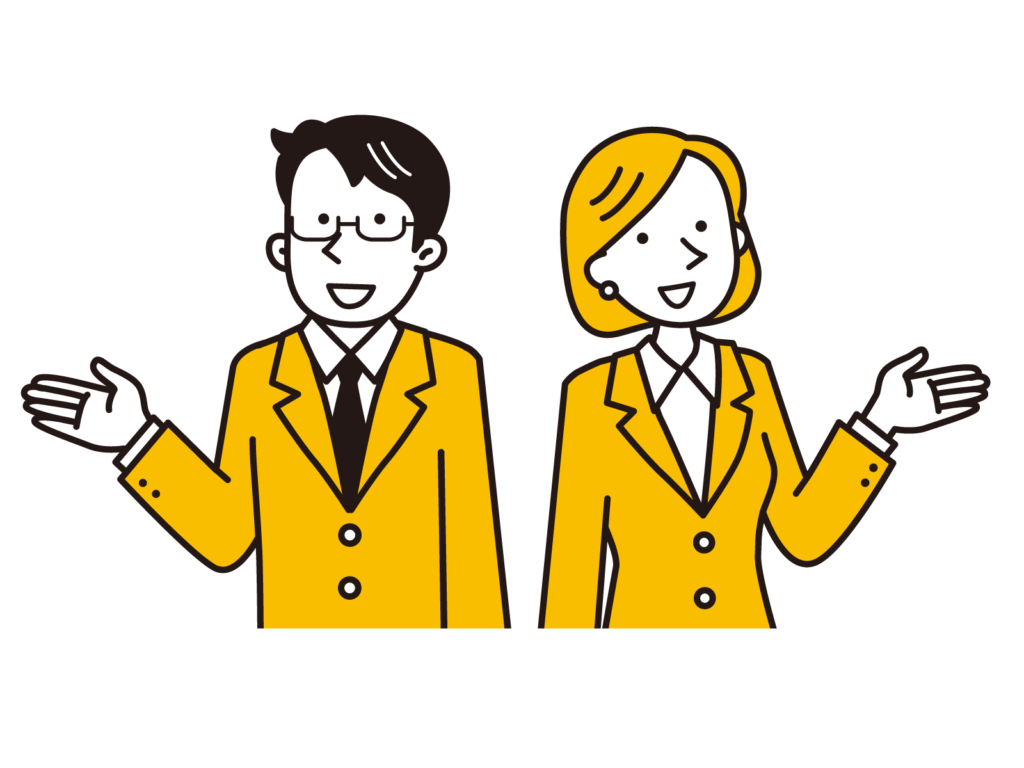
経営審査で提出する技術職員名簿に記載ができる対象者は、申請する事業者の審査を受ける決算日(審査基準日)からさかのぼって6か月を超えて在籍している技術者の方に限られています。同じ年に2社以上の技術職員としてカウントできないように制限がかけられているのです。
対象となる資格は建設業許可において、主任技術者となれる資格、学歴、実務経験を有している方と同じです。審査会場では各資格の証書、卒業証明書の写しが必要です。実務経験年数については、別に作成した職員名簿を審査員に提示します。申請する事業者に入社する前に経験した年数も加算することができます。尚、専任技術者の実務経験を証明するような資料を用意する必要はありません。

経営審査において職員が在籍している、ということは申請する事業者の所定勤務日を継続して勤務している者を指しています。よって健康保険・厚生年金に加入していること、役員等の適用除外された方以外は、さらに雇用保険にも加入していることを原則としています。非常勤の役員、パート、アルバイトのような方は対象外です。尚、定年退職後に年度更新の再雇用をされている方で、監督署に届け出た継続雇用制度の対象となっている場合には、技術職員の対象になります。
健康保険・厚生年金に加入する義務のない事業者や技術職員の場合には、別の手段で在籍していることを証明します。例えば後期高齢者となっている役員については税務申告書の勘定科目内訳書(役員報酬の内訳)で確認します。また個人事業主の家族の場合には確定申告書の専従者欄で確認をします。
出産、育児、介護、傷病などの理由で一時的に出勤されていない場合でも、健康保険・厚生年金の加入が継続していれば、正当な理由ありとして在籍が認められます。グループ会社等で出向社員を受け入れている場合も、会社間の契約書と出向先で給与等の費用を負担している請求書等の資料が提示できれば、出向先の技術職員として記載をすることができます。
この記事の内容は静岡県の申請要領を基にしておりますので、詳細は申請先の許可行政庁に確認をお願いします。
関連記事
経営事項審査とは?手続きの流れと事前に準備しておくこと
技術職員名簿の業種選択は経審の直前で対策できる審査項目
証明書類について

審査基準日以前に6か月を超える恒常的雇用関係の確認ができる次の①及び②を提出します。②に関しては技術職員名簿に記載されている技術者については省略ができます。
①常時雇用の確認書類
・申請時点直近の健康保険、厚生年金保険標準報酬決定通知書もしくは住民税特別徴収税額通知書の写し
・定年の記載がある部分の就業規則(60歳以上の技術者が記載されている場合のみ)
②6か月超前からの雇用の確認書類
・健康保険証もしくは雇用保険被保険者資格者等確認通知書の写し(いずれも所属企業の記載があるもの限定です)
■高年齢者雇用安定法の継続雇用制度対象者(6か月超前からの雇用者)
・継続雇用制度の適用を受けている技術職員名簿
・常時10人以上の労働者を使用する企業は、併せて継続雇用制度について定めた労働基準監督署の受付印のある就業規則
※定年を過ぎた技術者については、役員、継続雇用制度対象者(65歳以下に限る)及び個別の雇用契約書等で特に期間限定をすることなく常時雇用されていることが証明できる場合を除いて、「雇用期間を特に限定することなく常時雇用されているもの」に当たらないとみなされます(加点対象外)。
■出向者(出向先に常勤であれば加点対象となる可能性があります)
・出向協定書または出向契約書(出向内容等の詳細が記載されていない場合、それらが記載されている覚書等も併せて提出します)
※出向起算日から審査基準日までに6か月を超える恒常的雇用関係があることが条件となります。
みそらの経審サポートについてのご案内

みそら では、結果通知書の点数だけでなく、改善点についても専門的なアドバイスを提供しています。評価点数の向上が目指せるだけでなく、将来的な業務の効率化や成長にもつながります。まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
決算時サポート(スポット契約)
経営状況分析申請、決算終了後の変更届、経営規模等審査申請の一式をサポートします。
料金目安:15万円~20万円
※業種の数、完成工事高、兼業事業の状況、従業員数などにより作業量が変動するため、ヒアリング後にお見積りいたします。
戦略的経審Free(フリー)
無料で経審結果通知書を診断し、「問題点」や「改善が必要な取り組み」をアドバイスします。経営事項審査へのお悩みにも解決策をご提案いたします。
戦略的経審SpotConsulting(スポットコンサルティング)
経審申請書や添付書類を確認し、過去の通知書や経営状況を分析。今期に向けた具体的な対策をご提案します。
料金:1回 5万円(税込)
戦略的経審Consulting(月次コンサルティング)
~経審のための目標設定と事業計画~
受注したい発注先や発注金額、工事内容、件数を想定し、最適な格付(ポジション)を見極めます。そして、次回の経審に向けた目標を設定し、月次の情報交換・ミーティングを通じてPDCAを実施。経営状況分析や決算終了後の変更届、経営規模等審査申請など、全ておまかせしたい方におすすめのプランです。
スタンダードプラン 1ヶ月 38,500円(税込)(2業種・技術職員10名まで)
業種加算 評価する1業種ごと+2,200円(税込)
人数加算 技術職員10名ごと+2,200円(税込)
※業種の数、完成工事高、兼業事業の状況、従業員数などにより作業量が変動するため、ヒアリング後にお見積りいたします。
\まずはお気軽に無料相談をご利用ください/
無料で経審結果通知書を診断し、「問題点」や「改善が必要な取り組み」をアドバイスします。経営事項審査へのお悩みにも解決策をご提案いたします。
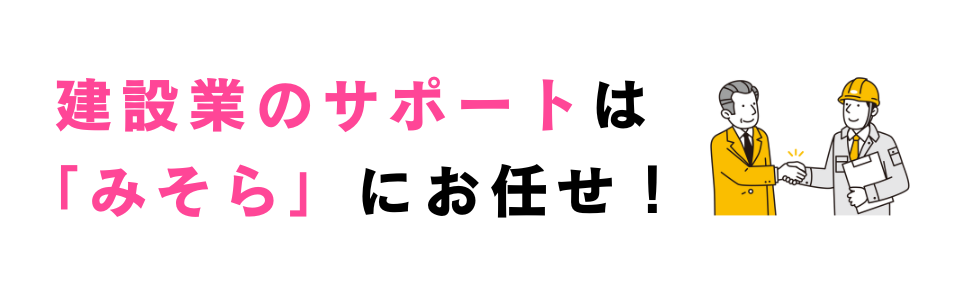

「経審の点数をより良くしたい…!」
「経審の点数を最適化して公共工事をより良い条件で受注したい…!」
無料ダウンロード 経審の見かたのポイントはこちらからダウンロードいただけます。



 www.misora-kensetsukyoka.com
www.misora-kensetsukyoka.com