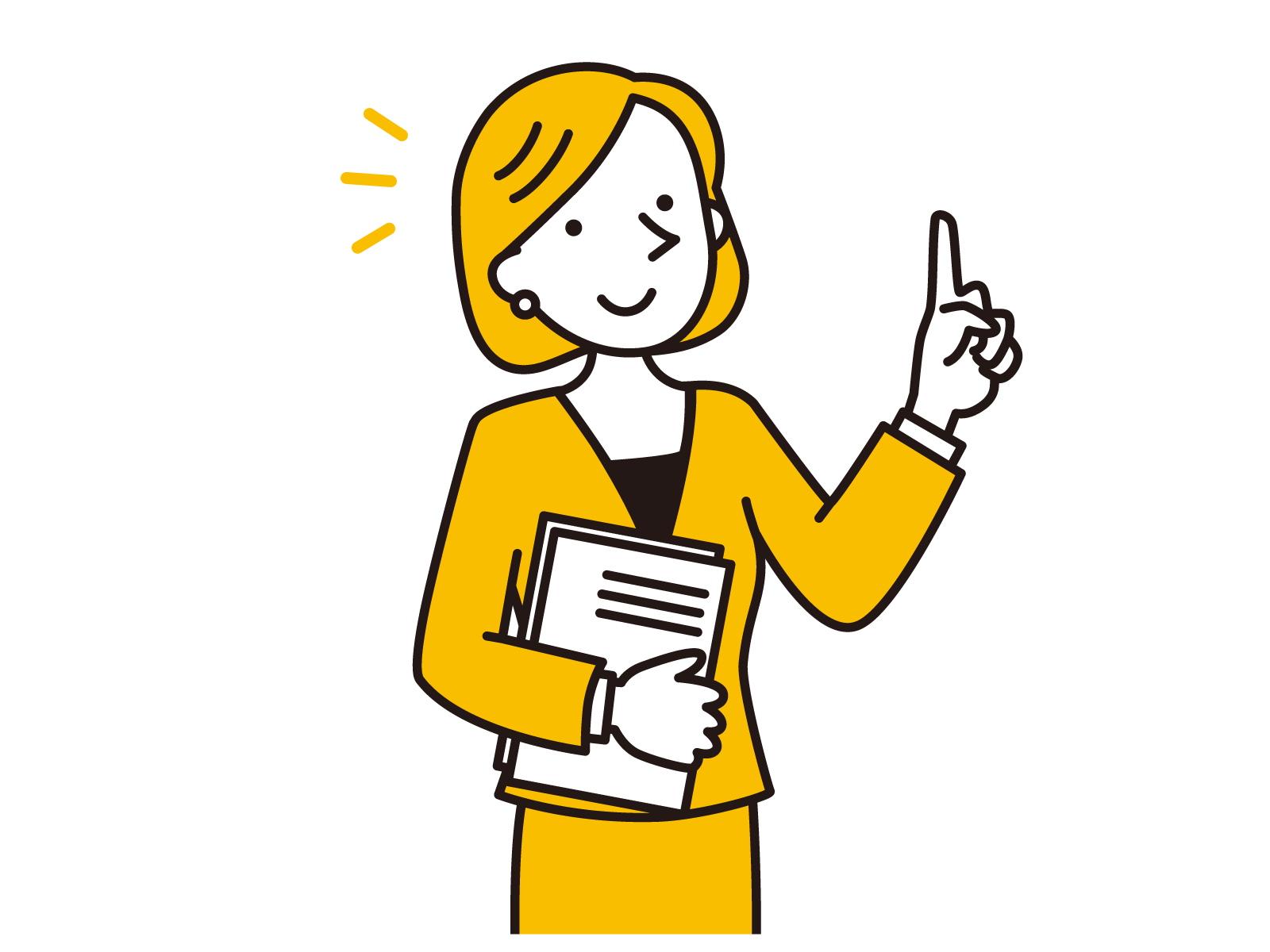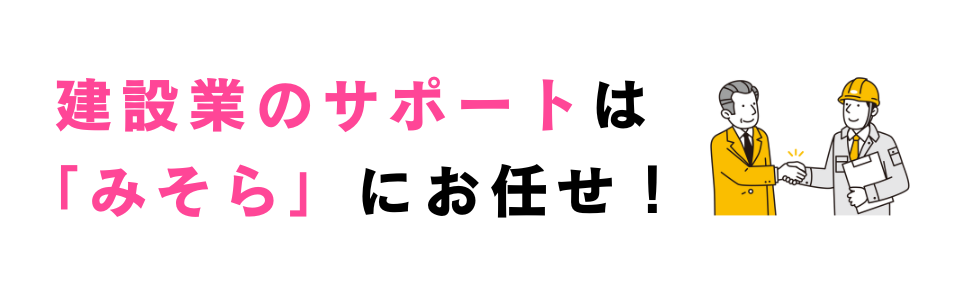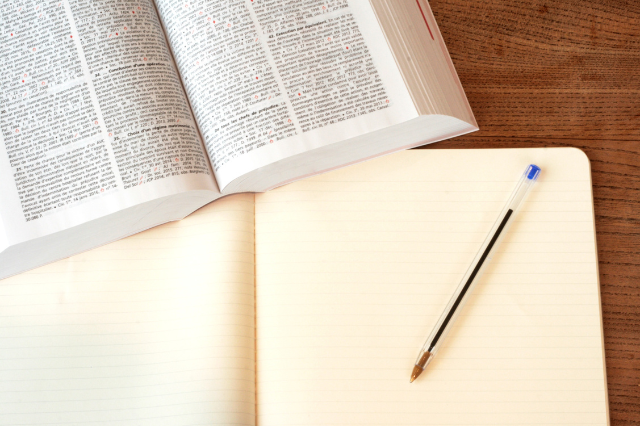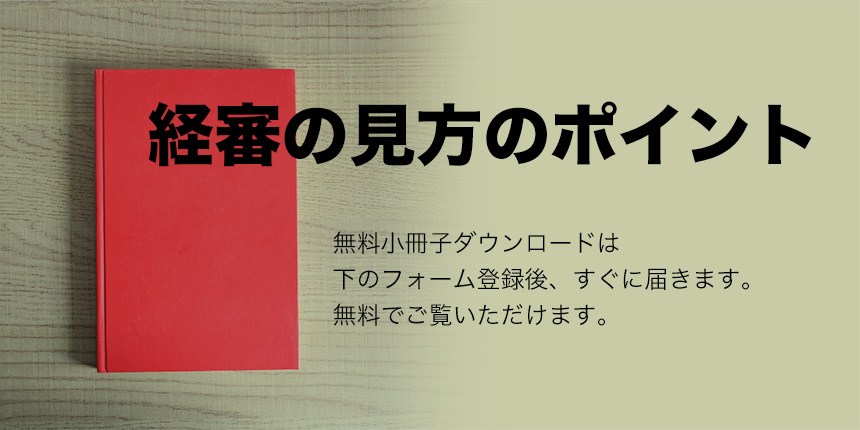建設業の財務諸表のなかに「完成工事原価報告書」があります。現場で直接かかった経費をそのほかの経費と分けて計算するものです。完成工事高(売り上げ)から完成工事原価を引いた金額が粗利になります。
本業である建設工事からどれだけ利益が出ているか、また出さなければならないのかを検証するための大事な計算になりますね。
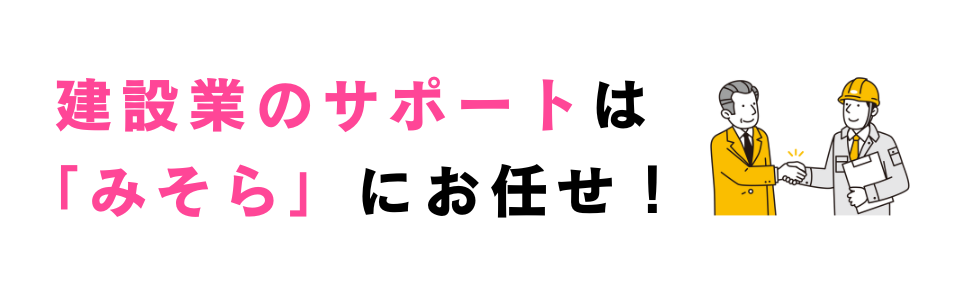

1.材料費
工事のために直接購入した素材、半製品、製品、材料貯蔵品等から振り替えられた材料費のことです(仮設材料の損耗額を含める)。前期末の在庫があり、事業年度内に材料を購入する必要がなかった場合は材料費は0円と記載します。
2.労務費
現場で工事に従事した直接雇用している作業員に関する賃金、給料および手当等を記載します。(人件費には作業員に対する社会保険料などの法定福利費も含みます。)建設業では工事を行う際に他社に仕事を依頼することが多いと思います。他社や個人事業主に依頼をした場合は労務費ではなく外注費に該当します。しかし、「材料や道具を自社で用意し、他社が工事のみを行う」場合や、「他社に人員不足を補うための応援を依頼」した場合、「外注先から受領した請求書の内容で経費の大部分が労務費」の場合には外注費ではなく労務費の中の「労務外注費」に分類されます。
3.外注費
外注費から労務外注費を引いた残りの額。一般的には他社の人が工事をする場合は外注費か労務外注費に含めます。外注費は「作業内容に対して」報酬が支払われます。給与の場合は時給や日給など、働く時間が決まっていてその時間に対して報酬が支払われます。外注費は時間的縛りがなく、外注先自身が就業時間を決定できます。時間的拘束を受けず、作業内容に対して報酬が支払われるものは「外注費」、時間的なしばりがある場合は「給与」と判断ができます。
4.経費
完成工事について発生し、または負担すべき経費から上記の3つの経費を引いた残りの額。
動力用水光熱費、機械等経費、設計費、労務管理費、租税公課、地代家賃、保険料、退職金、法定福利費、福利厚生費、事務用品費、通信交通費、交際費、補償費、雑費等。
賃金、給料および手当のうち、現場代理人や施工管理等、2の労務費に該当しない従業員の人件費。
このうち人件費については抜き出して「うち人件費」としても記載します。「うち人件費」には従業員給料手当、退職金、法定福利費、福利厚生費が含まれます。
1~4の合計額が、損益計算書の完成工事原価と一致しているか確認をしましょう。

最後に役員報酬について注意したい点をご説明します。
少人数の会社の場合、役員が直接工事に関わっていることが大半です。
役員の報酬は完成工事原価ではなく、一般管理費の中の役員報酬として、計上されていますが、直接工事に関わった部分の報酬は完成工事原価の経費(うち人件費)に振り分けることができます。
このほうが実際の工事原価を把握する近道になりますね。
5.まとめ
顧問の税理士等が作成した決算報告書には、原価として棚卸高の記載はあっても完成工事原価報告書がない場合があります。また外注費や現場に従事する社員の給料が全て一般管理費に計上されている損益計算書も目にします。税務上は問題が無いとしても、建設業の変更届や経審を受ける場合には、建設業法のルールに沿って建設財務諸表として作成し直さなければなりません。
これは確定申告が済んだ後の建設業法の手続き上の問題ですが、そもそも完成工事原価の把握が出来ていなくて、一件ごとの工事原価の管理、利益の確保が可能なのかが疑問です。もっと利益の出る体質にしたい、という希望がありましたら、一度、私共までご連絡をいただければと思います。