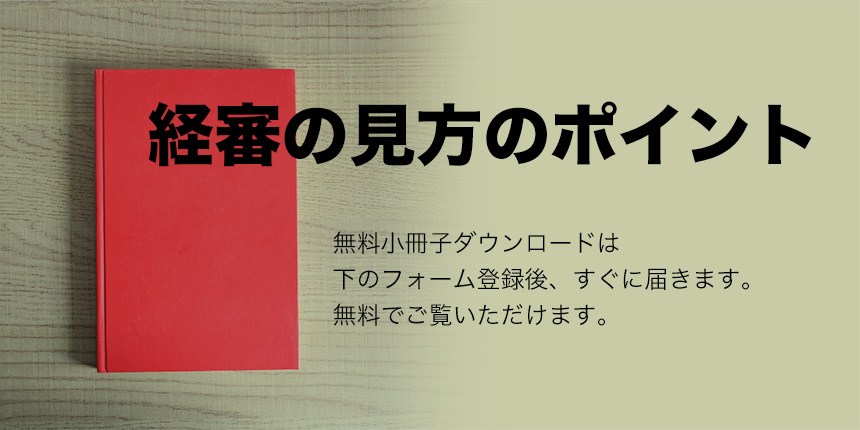~目次~
専任技術者の役割
専任技術者が常勤であることの証明する方法
専任技術者になれる資格と実務経験
専任技術者の資格を実務経験で証明する方法
建設工事の内容について
土木一式工事の許可に必要な資格
建築一式工事の許可に必要な資格
機械器具設置工事業に必要な実務経験
専任技術者と主任技術者
現場に配置する専任の技術者について
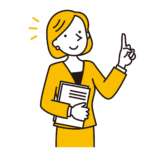
建設業許可を取得して公共工事を請け負おうとする場合には、許可の取得だけでなく「経審(経営事項審査)」を受ける必要があります。経審についてはこちらの記事をご確認ください。
関連記事 なぜ経審の点数を良くする必要があるのか?
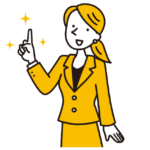
重要 経審の見かたを覚えて点数を最適化していけば、利益率が高まります!経審の見かたをダウンロードしてさっそく1年目からチェックしてみてください!ダウンロードはこちら。
専任技術者の役割

建設業許可を申請する際には、専任技術者の設置が必要です。専任技術者は会社に専属で勤務し、在籍する営業所の請負契約に関する見積もり、入札、契約締結等に関して技術的な専門知識を発揮する立場です。営業所でのデスクワークが主になります。
建設業許可を取得した後に現場に配置する必要があるのが主任技術者です。主任技術者は担当する工事について、施工計画の作成、工程の管理、資材の調達、安全の管理などを行います。工事現場での指揮命令が主になります。
名前が似ていますが、建設業法ではそれぞれ別の役割を求められています。しかし社員数の少ない事業者では、専任技術者と主任技術者を同じ方が兼任することが多くあります。後述しますが、専任技術者を現場に配置する技術者として認められるには条件があります。
関連記事 建設業許可についての詳しい解説はこちら
専任とは?
「専任」とは、ある営業所に常勤し、その職務に専念することを指します(テレワークを行う場合を含む)。雇用契約に基づいて事業主体と継続的な関係を持ち、休日その他勤務を要しない日を除き、通常の勤務時間中はその営業所に勤務し、建設工事に関する請負契約の適正な締結及びその履行を確保しなければなりません。ただし、以下の場合は原則として「専任」とは認められません。
- 技術者が営業所から遠距離に住んでおり、通勤が実質的に不可能な場合(テレワークを行う場所も含む)。
- 他の営業所で専任を要する職務を行っている場合。
- 建築事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引士等、他の法令により特定の事務所等において専任を要することとされている者。(例外:同一法人内、同一営業所内であれば兼務が可能)
- 報酬や賃金が著しく低い場合(正当な理由がある場合を除く。) など。
専任技術者が常勤であることを証明する方法

専任技術者の有資格者が常勤であることを証明する方法ですが、静岡県の規定を例にご案内いたします。(許可行政庁ごとに異なりますので必ずご確認ください。)
建設業法の改正で令和2年10月1日以降は社会保険加入義務のある事業者は、社会保険に加入してることが建設業許可の条件となりました。
1.原則:社会保険の健康保険証のコピー(申請日時点で社会保険加入していることの確認)
2.個人事業主:国民保険被保険者証のコピー
3.従業員で後期高齢者のため社会保険に加入していない方:雇用保険のコピー(申請日時点で雇用保険に加入していることの確認)
4.従業員で社会保険・雇用保険に加入していない方(事業主の家族など):賃金台帳のコピー
尚、会社を設立したばかりで社会保険の加入手続きは取っているものの手元に保険証が届いていない場合には、社会保険の加入手続きの際に年金事務所に提出した届出の控えを提出します。
専任技術者になれる資格と実務経験

専任技術者となるための実務経験年数は10年といわれます。ただし学歴によって年数が短くなることも押さえておきましょう。専任技術者になるためには、以下の①~③いずれかを満たしている必要があります。
①10年以上の実務経験がある
②指定学科を卒業しており、学歴に応じた実務経験がある
③定められた国家資格等を取得している
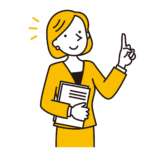
関連記事 営業所専任技術者となり得る国家資格についての記事はこちら。
業種ごとに必要な国家資格等や実務経験の期間をご確認いただけます。
学歴とは、具体的には許可を取りたい業種にあった学科を卒業していることです。②の指定学科と実務経験については以下のとおりです。
1.高等学校(全日のほかに、通信、定時含む):5年
2.専門学校(専修学校専門課程):5年
3.専門学校(専門士、高度専門士過程):3年
4.高等専門学校:3年
5.短期大学:3年
6.大学:3年
※7.技士 又は 技士補(1級1次検定合格 対応種目):3年
※8.技士 又は 技士補(2級1次検定合格 対応種目):5年
※令和5年7月1日施行 《一般建設業許可の営業所専任技術者の要件の緩和》
専任技術者の資格を実務経験で証明する方法

専任技術者の条件を満たすことの証明方法は、資格の保有または実務経験のどちらかです。
提示する書類のパターン
1.国家資格の合格証、カード等のみ
2.国家資格の合格証、カード等+実務経験証明書
3.卒業証明書、成績証明書+実務経験証明書
4.実務経験証明書
それぞれの業種に対応した国家資格(一部は民間資格あり)を取得しているか、学歴に応じた実務経験を積んでいることを裏付ける資料を提出します。この実務経験ですが、現場の責任者としての立場による経験に限らず、見習い等でも構いません。役職よりもとにかく現場での施工の経験を重要視しています。
資格があることのメリットは、実務経験がない業種でもついでに許可が取れてしまうことです。例えば、実務経験としては内装工事だけであっても、仮に二級建築施工管理技士(仕上げ)をお持ちであれば、内装の他に、大工、左官、石、屋根、タイルレンガブロック、板金、ガラス、塗装、防水、熱絶縁、建具、以上の12種類も許可が取れることになります。
資格がとても優遇されていることが分かりますね。「忙しくて資格を取る暇もない」場合は、次のことを注意しながら「実務経験」を証明することになります。
実務経験は「何年」必要なのか?
年数については、原則として1つの業種に対して10年が必要という考え方をします。例えばひとりの職人さんが仕事についてから15年間、塗装工事と防水工事に携わったとします。
この二つの工事は並行して経験している訳ですが、建設業許可の審査となるとどちらか一方で10年間となるため、残りは5年しか経験がない、という解釈になります。先に塗装の経験を優先した場合には、防水の実務経験を証明するのにあと5年先まで待たなければなりません。
原則10年といいましたが、例外としては5年と3年があります。
これは許可を取ろうとする業種に関連している学科を高校や大学などで勉強したことを条件として、実務経験の年数を減らしてくれる制度です。
【実務経験3年】
大学、短期大学、高等専門学校、専門学校(高度専門士課程、専門士課程)、技士 又は 技士補(1級1次検定合格 対応種目)
【実務経験5年】
専門学校(専修学校専門課程)、高等学校、中高一貫校、技士 又は 技士補(2級1次検定合格 対応種目)
ではどんな学科を卒業していればよいか?となりますが、次のとおりです。
土木工事業:土木工学、都市工学、衛生工学、交通工学
舗装工事業:同上
建築工事業:建築学、都市工学
大工工事業:同上
ガラス工事業:同上
内装仕上げ工事業:同上
左官工事業:土木工学、建築学
とび・土工・コンクリート工事業:同上
石工事業:同上
屋根工事業:同上
タイル・レンガ・ブロック工事業:同上
塗装工事業:同上
解体工事業:同上
電気工事業:電気工学、電気通信工学
電気通信工事業:同上
管工事業:土木工学、建築学、機械工学、都市工学、衛生工学
水道施設工事業:同上
清掃施設工事業:同上
鋼構造物工事業:土木工学、建築学、機械工学
鉄筋工事業:同上
しゅんせつ工事業:土木工学、機械工学
板金工事業:建築学、機械工学
防水工事業:土木工学、建築学
機械器具設置工事業:建築学、機械工学、電気工学
消防施設工事業
熱絶縁工事業:土木工学、建築学、機械工学
造園工事業:土木工学、建築学、都市工学、林学
さく井工事業:土木工学、鉱山学、機械工学、衛生工学
建具工事業:建築学、機械工学
実務経験とはどんな内容の仕事なのか

では実務経験とは、一体どんな経験を証明すればいいのか?という疑問があるかと思います。
建設業許可の審査でいう実務経験とは、建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいい、建設工事の発注にあたって設計技術者として設計に従事し、又は現場監督技術者として監督に従事した経験、さらに作業員、見習いとして現場に従事した経験も含みます。ただし雑務のみは経験に入りませんので注意が必要です。
どんな書類が必要になるのか
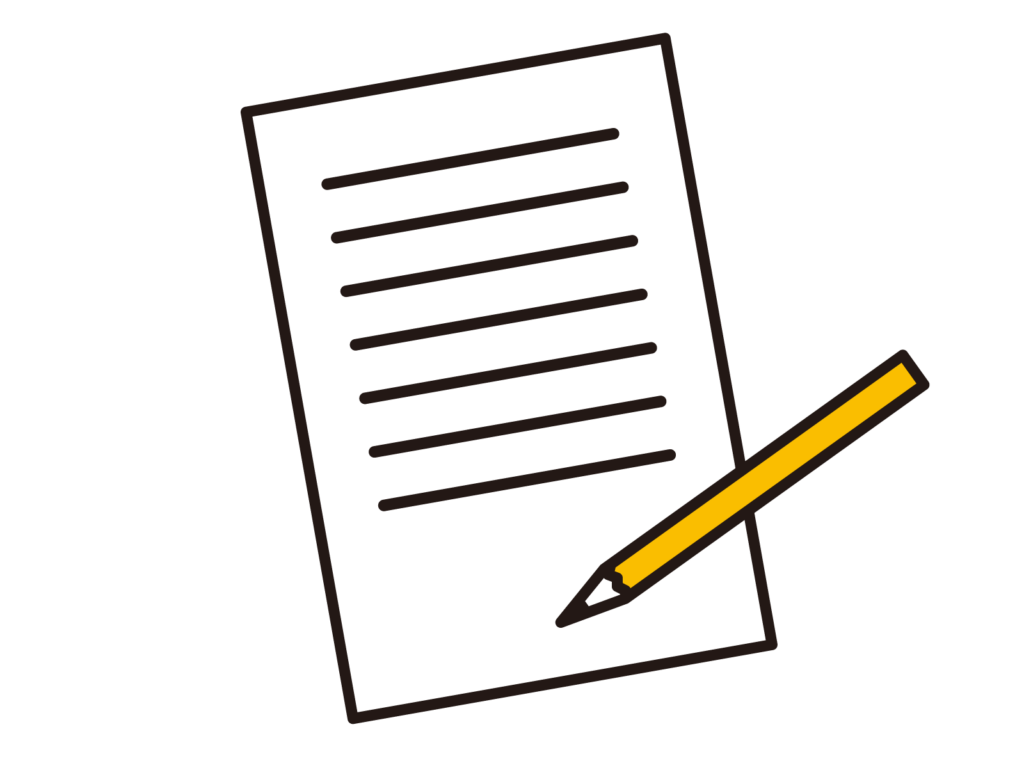
①技術者、技能者または見習いとして携わった工事の内容を証明するもの
②その工事の際に常勤していたことを証明するもの
①工事の内容については、大きく分けて3種類あります。
(ここでは静岡県の規定を例にご案内しますが、許可行政庁ごとに異なります。)
「請負契約書」 建築一式工事の場合には更に建築確認も必要です。
「注文書」
「請求書プラス通帳」請求を月でまとめている場合はその一覧も必要です。
②その時に常勤していたかどうかは、いくつか選択肢があります。
会社に勤めていた時は、健康保険証、厚生年金の回答票、源泉徴収票及び所得証明書、役員なら法人税確定申告書の別表1及び役員報酬の内訳書、住民税特別徴収の決定通知書、以上のいずれかがあれば良いです。
個人事業主であれば確定申告書及び所得証明書があれば良いです。
当然ですが、証明しようとする期間のすべてについて必要です。
実務経験を証明するための注意3点

1.実務経験の年数は何年あればよいか?足りているか?
2.実務経験の仕事の内容は取りたい許可業種と合っているか?
3.年数と内容を証明する書類は揃えられるか?
以上を確認してみてください。
建設工事の内容について

土木一式工事の許可に必要な資格

建築一式と並んで総合的な企画・調整を要するのが土木一式工事です。土木系の工事業者様にとっては取得のニーズが高い業種です。
しかし実務経験を証明するには、道路・水路・下水道の築造工事など、元請の公共工事にほぼ限られているため、下請け工事で開業した方は自社で実務経験を証明できる可能性はかなり低いと思います。どんな国家資格があれば土木一式工事の許可が取れるのでしょうか。
・1級建設機械施工技士
・2級建設機械施工技士(第1種~第6種)
・1級土木施工管理技士
・2級土木施工管理技士(土木)
・技術士(建設・農業土木・水産土木・森林土木 ※一部省略)
以上の資格になります。資格の種類は限られていますが、土木系の国家資格のなかでも、建設機械施工技士は比較的チャレンジし易い資格であると伺います。
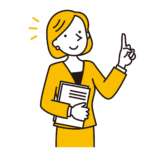
関連記事 営業所専任技術者となり得る国家資格についての記事はこちら。
業種ごとに必要な国家資格等や実務経験の期間をご確認いただけます。
建築一式工事の許可に必要な資格

この許可は実務経験で取得するのが難しいことは土木一式と同様です。建築一式の定義を、建築確認の手続きが必要な、新築、増築、大規模修繕に限って静岡県は実務経験を認めているため、経験を裏付ける資料としても、工事請負契約書プラス建築確認済証(検査済証)に限定しているためです。※一部に例外はあります。
ではどの資格を持っていれば実務経験を証明することなく、建築一式工事業の専任技術者となることができるのでしょうか。
・1級施工管理技士
・2級建築施工管理技士(建築)
・1級建築士
・2級建築士
以上です。これしかありません。
それだけ責任の重い工事であると行政が考えている、ともいえます。
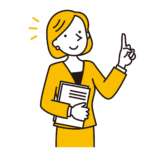
関連記事 営業所専任技術者となり得る国家資格についての記事はこちら。
業種ごとに必要な国家資格等や実務経験の期間をご確認いただけます。
機械器具設置工事業に必要な実務経験

機械器具設置工事業の許可を取るための資格は、技術士の機械(一部省略)のみです。技術士はコンサルタント会社以外ではあまりなじみのない資格です。難易度も非常に高いと伺っています。現場で必要とされている方は現実的には実務経験で証明していくほかありません。しかし実務経験の内容も非常に特殊で限られています。
一般に機械器具を取り扱う業界では、機械器具設置工事業の許可を有することが取引条件となっている事例もよく伺います。しかし建設業法においては一般の認識よりもかなり「狭い」分野しか認めていません。国の告示では次のように定義されています。
機械器具の組み立て等により土木若しくは建築に関する工作物を建設する。
具体的には以下の文言が列挙されています。そこに民間の施設として事例を付記してみます。
・プラント設備:廃棄物処理施設
・給排気機器
・舞台装置設備
・運搬機器:エレベーター、クレーン(ホイスト)
・揚配水機器
・サイロ設備
・内燃力発電設備
・ダム用仮設備
・立体駐車場:立体駐車場
・集塵機器
・遊戯施設
上記にもいくつか「機器」という文言がありますが、比較的小さな機械のことを指してはいません。建物と一体で用をなしている大きな設備です。
工場や事業所のラインに設置されている一連の機械を機械器具設置工事としたい、というご相談は非常に多いです。しかし商品生産設備として使用される機械の設置は、とび・土工・コンクリート工事として扱われます。ここに現実の取引状況と法令との乖離があります。
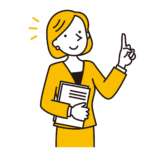
専任技術者と主任技術者

専任技術者の役割でもご案内しましたが、建設業許可を申請する際に、必要なのは専任技術者です。そして許可を取得した後に現場ごとに配置するのは主任技術者です。
主任技術者は担当する工事について、施工計画を作成し、工程を管理し、資材の調達、安全の管理などを行う立場です。工事現場での指揮命令が主になります。名前は似ていますが、建設業法ではそれぞれ別の役割を求められています。しかし社員数の少ない事業者においては、専任技術者と主任技術者を同じ方が兼任することが多くあります。
ところで、請負工事金額が税込みで4,000万円以上(建築一式工事は8,000万円)の場合、その現場に「専任で」主任技術者を配置しなくてはなりません。規模が大きくなると、管理する仕事が多く責任が重くなります。
上記のように、ひとつの現場に専任の主任技術者をおかなければならないケースを除いては、専任技術者が主任技術者を兼任することができます。建設業許可を取得した後、毎年の決算ごとに提出する工事経歴書においては、この主任技術者が適切に配置されているか、ということも審査されています。
現場に配置する専任の技術者について

建設業法施行令の一部を改正する政令が令和5年1月1日に施行されました。
特定建設業許可が必要となる下請け契約金額の緩和
特定建設業許可を受けていなければならない下請け契約の金額を、現行の4,000万円から4,500万円(建築一式工事は6,000万円から7,000万円)に引き上げました。
技術者が現場専任となる工事請負金額の緩和
専任の主任技術者・監理技術者の設置が必要な工事請負金額を、現行の3,500万円から4,000万円(建築一式は7,000万円から8,000万円)に引き上げました。背景としては、現場を管理する技術者の減少と建設工事費の上昇が続いていることです。
1の特定建設業許可については、昭和46年に制度が出来たときには、下請け契約の金額は1,000万円でした。その後、2,000万円、3,000万円、4,000万円と引き上げられて現在に至ります。
2の現場専任となる工事請負金額については、昭和24年の建設業法が出来たときには200万円、その後、300万円、450万円、600万円、900万円、1,500万円、2,500万円、3,500万円と引き上げられて現在に至ります。
法律が出来てから70年以上経っているのですから、こうしてみると引き上げる回数が少ないように感じられます。見直しの背景のひとつ、技術者の減少については、バブル景気の崩壊以降に顕著になったので既に30年以上は経過していますし、もうひとつ建設工事費の上昇については、コロナ禍以降、特に顕著になっていることは明らかです。
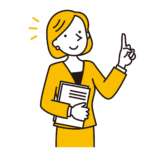
建設業許可を取得して公共工事を請け負おうとする場合には、許可の取得だけでなく「経審(経営事項審査)」を受ける必要があります。経審についてはこちらの記事をご確認ください。
関連記事 なぜ経審の点数を良くする必要があるのか?
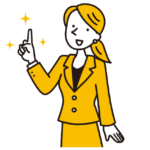
重要 経審の見かたを覚えて点数を最適化していけば、利益率が高まります!経審の見かたをダウンロードしてさっそく1年目からチェックしてみてください!ダウンロードはこちら。