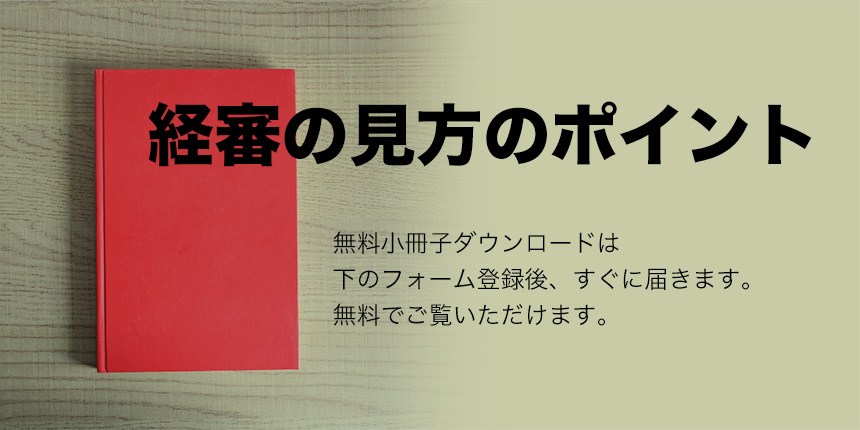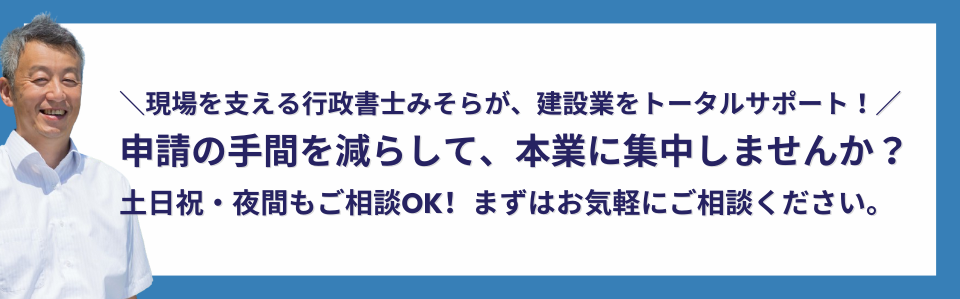
電気通信工事とは?その範囲と電気工事との決定的な違い
建設業許可と営業所(専任)技術者の要件
電気通信工事の現場に配置できる主任技術者の資格
施工管理技士の受験資格と実務経験
資格取得後の手続きと有効活用

電気通信工事とは?その範囲と電気工事との決定的な違い
電気通信工事の定義と具体的な工事内容
建設業法における電気通信工事とは、有線・無線・光ファイバーなどの電気通信設備を設置する工事のことを指します。
主な工事例
・LAN配線工事
・電話設備工事(PBXの設置など)
・光ファイバーの敷設
・携帯電話基地局の設置
・情報表示設備工事
・テレビ共同受信設備の設置 など
電気工事との違い
電気工事(電気事業法)
発電・送電・照明など、“電気を使うための設備”の工事(強電)。
例:照明、コンセント、動力設備など。
電気通信工事(建設業法・電気通信事業法)
情報を伝える設備の工事(弱電)。
例:LAN、光回線、電話、ネットワーク機器など。
電気工事は「大きな電力」を扱う工事です。一方、電気通信工事は情報通信設備に関連する小さな電力を扱う工事です。電気工事を行うためには、「電気工事士」や「電気主任技術者」などの国家資格が必要です。一方、電気通信工事を行うためには「工事担任者」や「電気通信主任技術者」などの国家資格が必要です。

電気通信工事業の建設業許可と営業所(専任)技術者の要件
電気通信工事業の許可取得・維持に欠かせないのが「営業所(専任)技術者」です。
営業所(専任)技術者として認められる資格
資格で満たす場合(実務経験不要)
・1級電気通信工事施工管理技士
・技術士(電気電子部門、総合技術監理部門〈電気電子〉)
資格がない場合(実務経験で満たす)
・指定学科の大学など卒業 → 3年の実務経験
・その他の学歴 → 10年の実務経験
資格者がいない場合でも、「10年の実務経験」を証明できれば営業所(専任)技術者になれます。しかし、行政庁へ提出する証明書類(請負契約書、発注書など)は、以下の要件を満たす必要があります。
・10年間の連続した実務経験を証明できること。
・経験した工事が電気通信工事であることを明確に示す客観的な証拠があること。
特に証明書類の収集と整理は非常に手間がかかります。実務経験を漏れなく証明できるか、弊所で事前診断いたします。
関連記事 営業所技術者(専任技術者)を実務経験で証明する方法
特定建設業と一般の違い
・一般建設業 … 上記資格または実務経験で可
・特定建設業 … 原則、1級電気通信工事施工管理技士 または 技術士(電気電子・総合技術監理(電気電子))が必須

電気通信工事の現場に配置できる主任技術者の資格
1級電気通信工事施工管理技士
【役割】
電気通信工事の施工計画作成、工程・品質・安全管理を担う国家資格です。
【主任技術者としての権限】
・電気通信工事業における主任技術者として、全ての工事現場に配置可能です。
・1級は特に、大規模な特定建設業の現場で監理技術者として、現場を統括する立場で活躍します。
【活用の場】
通信ケーブルの布設、通信機器の設置、ネットワーク設備の構築など、建設現場全般を統率します。
2級電気通信工事施工管理技士
【役割】
比較的小規模な電気通信工事の現場において、適正な施工管理を行う主任技術者の役割を担う国家資格です。
【主任技術者としての権限】
建設業法に基づき、一般建設業で請け負う工事現場に主任技術者として配置可能です。
【企業のメリット】
・企業が継続的に安定した工事を受注し、現場を適正に管理していくための基礎的な現場責任者資格です。
・1級技士へのステップアップを見据えた、若手・中堅社員の育成にも不可欠です。
1級電気通信工事施工管理技士補
【目的】
1級第一次検定(学科試験)合格者に与えられる称号です。
【役割】
1級技士補は、主任技術者の資格(2級施工管理技士や実務経験が10年以上など)を有することで、監理技術者の補佐となることができます。そして一定条件を満たした2つの現場を特例監理技術者が兼任することができるようになります。
【特徴】
実務経験がなくても、年齢(満19歳以上)の要件のみで第一次検定を受験できるようになったため、若手技術者の早期のキャリアアップに繋がる資格です。
技術士(電気電子部門・総合技術監理部門〈電気電子〉)
【役割】
科学技術分野における最上位の国家資格で、高度な専門知識と総合的な技術管理能力を証明します。
【主任技術者としての権限】
技術部門が合致すれば、実務経験を問わず、主任技術者・監理技術者として配置可能です。
【活用の場】
・電気電子部門:高度な技術的課題の解決や設計指導など、技術コンサルティングで知見を活かします。
・総合技術監理部門:組織全体の技術・品質・安全・経済性などを統括する技術経営の視点が評価され、大規模案件の受注に寄与します。
電気通信主任技術者(電気通信事業法)
【役割】
電気通信事業法に基づく国家資格で、通信事業者が保有する事業用電気通信設備の工事・運用・保守などを統括する技術責任者です。
【主任技術者としての権限】
通信キャリア(事業者)の事業場において、設備の安全で安定した運用を確保するための監督責任者として選任が義務付けられています。
【試験の種類と役割】
・伝送交換主任技術者:通信ネットワークの「頭脳」であり「心臓部」である局内設備(交換機、ルーター、多重化装置など)の運用・保守を監督します。
・線路主任技術者:通信ネットワークの「血管」であり「神経」である物理的な伝送路(光・メタルケーブル、電柱、管路など)の工事・維持・運用を監督します。
工事担任者
工事担任者の資格者証の交付を受けた後、電気通信工事の実務経験が3年以上ある者
(第一級アナログ通信及び第一級デジタル通信の資格者証の交付を受けた者又は総合通信の資格者証の交付を受けた者に限る。)
令和4年度からは、工事担任者試験の内容に「工事の施工管理」分野が追加され、より実務的な知識が重視されるようになりました。これに伴い、建設業法上の主任技術者の要件に「工事担任者」が新たに加えられたと考えられます。ただし、この改正の適用対象は令和3年4月1日以降に試験に合格した方、または養成課程を修了した方からとなります。また、主任技術者として認められるためには、資格者証の交付後に電気通信工事の実務経験が3年以上必要です。そのため、令和4年度に合格された方の場合、令和7年度から主任技術者として配置可能となる見込みです。
【役割】
電気通信事業法に基づき、利用者の端末設備(電話、FAX、ルーター等)や自営電気通信設備(PBX等)を、電気通信事業者の回線に接続する工事の実施または実地監督を行う技術者です。
【工事の具体例】
電気通信事業者の通信設備(保安器、ONU等)に通信線を接続する工事(ネットワーク機器のセットアップ、配線工事、通信障害時の切り分け・復旧工事 等)
| 第一級アナログ通信 | アナログ回線及びISDN回線に端末設備等を接続するための工事全て |
| 第二級アナログ通信 | 1回線のアナログ回線及び基本インターフェースが1回線のISDN回線に端末設備等を接続するための工事 |
| 第一級デジタル通信 | デジタル回線(ただしISDN回線を除く)に端末設備等を接続するための工事(以下「デジタル工事」という。)全て |
| 第二級デジタル通信 | デジタル工事の内、1Gbps以下のインターネット接続工事 |
| 総合通信 | アナログ回線及びデジタル回線に端末設備等を接続するための工事全て |

施工管理技士の受験資格と実務経験
特に多くのご質問をいただくのが、「自分は試験を受けられるの?」「どんな工事が実務経験として認められるの?」という点です。施工管理技士の受験資格と、実務経験の範囲について、詳しく見ていきましょう。
1級・2級施工管理技士の受験資格をチェック!
試験を受けるためには、原則として定められた年数の実務経験が必要です。
受験に必要な経験年数
最終学歴(大学、短大、高校など)や卒業された学科が「指定学科(電気通信工学、情報工学など)」であるかどうかによって、卒業後の実務経験年数が細かく決まっています。ご自身の経歴と照らし合わせて確認が必要です。
| 最終学歴 | 1級(第一次検定)必要な実務経験 | 2級(第一次検定)必要な実務経験 |
| 大学(指定学科卒業) | 3年以上 | 卒業後3年(指定学科なら1年6ヶ月)以上 |
| 大学(指定学科以外) | 4年6ヶ月以上 | 卒業後3年以上 |
| 短期大学・高等専門学校(指定学科卒業) | 5年以上 | 卒業後2年以上 |
| 短期大学・高等専門学校(指定学科以外) | 7年6ヶ月以上 | 卒業後3年以上 |
| 高校(指定学科卒業) | 8年以上の実務経験 | 卒業後3年以上 |
| 高校(指定学科以外) | 11年6ヶ月以上の実務経験 | 卒業後3年以上 |
指定学科とは?
電気通信工学、情報工学、電気工学など、国土交通大臣が定める学科を指します。ご自身の卒業された学科が指定学科に該当するかどうかの確認が必要です。
早期受験のチャンス(第一次検定)
現在、施工管理技士の第一次検定(旧:学科試験)については、受験資格が緩和されています。特に2級では、実務経験が短縮されたり、満17歳以上であれば受験できたりするルートもありますので、早い段階で資格取得の準備を始める戦略が非常に重要になっています。
実務経験として認められる工事の具体的な範囲
建設業の許可や資格において求められる「実務経験」とは、単に工事現場で働いていた経験ではありません。
原則
営業所(専任)技術者や主任技術者の要件として認められる実務経験は、その業種の「建設工事」であることが大前提です。つまり、電気通信工事の資格であれば、光ファイバー敷設、LAN構築、電話設備設置など、電気通信工事として認められる実績が必要です。
ここが専門的な判断ポイント
実際には、複数の業種が混ざった工事(複合工事)が多いですよね。その工事内容が本当に「電気通信工事」として認められるのかどうかは、以下の資料に基づき、厳密に判断しなくてはいけません。
行政書士の専門性
うちの昔の通信工事、これで実務経験にカウントできるかな?」と迷われたら、ぜひ私たちにご相談ください。お客様の過去の工事資料を一つひとつ丁寧に確認し、法的根拠に基づいて「受験資格を満たしているか」を判断するお手伝いをいたします。

資格取得後の手続きと有効活用
社員さんが頑張って資格を取った後、会社として適切な手続きを踏むことで、その資格はただの証明書で終わらず、会社の信用力や売上アップに直結する大きな武器になります。
資格取得後の「変更届」を忘れずに!
資格を取った後の手続きの中で、見落とされがちなのが「変更届」の提出です。
なぜ必要?
建設業の許可は、「営業所(専任)技術者」がいることを前提としています。営業所(専任)技術者を変更する際は、変更があった日から14日以内に届出が必要となります。
手続きの対象
・営業所(専任)技術者の変更する際
行政書士からの注意
届出を怠ったり、期限を過ぎて提出したりすると、建設業法違反となり、許可取り消しの可能性もあるため注意が必要です。
経営事項審査(経審)で会社の実力をアピール!
資格取得は、公共工事の受注に欠かせない経審で、貴社の技術力を証明し、評価点(点数)を上げるための最大の要因の一つです。
技術力(Z点)の加点
1級、2級の電気通信工事施工管理技士や技術士を技術職員名簿に登録することで、経審の技術職員数としてカウントされ、会社の技術力評価点(Z点)が大きく向上します。複数資格を持つ技術者は、どの業種でカウントさせるかを計算し、Z点が最も高くなるように戦略的に配置します。
弊所では、この名簿の作成から届出、そして経審対策としての最適配置をアドバイスしています。
具体的な活用
経審の点数が上がれば、入札参加資格における競争力が向上し、より大きな工事や、これまで受注が難しかったランクの工事にチャレンジできるようになります。
電気通信工事業の技術職員名簿に掲載できる資格
1.一級電気通信工事施工管理技士
2.二級電気通信工事施工管理技士
3.技術士(電気電子・総合技術監理)
4.電気通信主任技術者
5.実務経験
6.工事担任者
1級技士補を「戦略的」に活用する
新しく導入された1級電気通信工事施工管理技士補の資格は、特に大規模工事を受注する企業にとって、非常に戦略的なメリットをもたらします。
監理技術者の兼務緩和
従来、大規模な工事現場の責任者である「監理技術者」(1級技士)は、原則として一人の現場に専任する必要がありました。しかし、技士補を現場に配置することで、監理技術者が2つまでの工事現場を兼務できるようにルールが緩和されました。
受注機会の拡大
これは、技術者が不足している状況で、貴社が複数の大規模工事を同時に請け負えることを意味します。工事の効率化と、受注機会の最大化に直結します。
【専門家がサポート】貴社の資格要件チェックと申請手続き
「資格者が増えたから変更届を出したい」「経審で加点を最大限に活かしたい」「複雑な実務経験で受験資格を満たすか診断してほしい」など、資格や建設業許可に関するお悩みは、建設業に特化した私たち行政書士がサポートいたします。お客様の事業がスムーズに進むよう、しっかりとお手伝いさせていただきます!
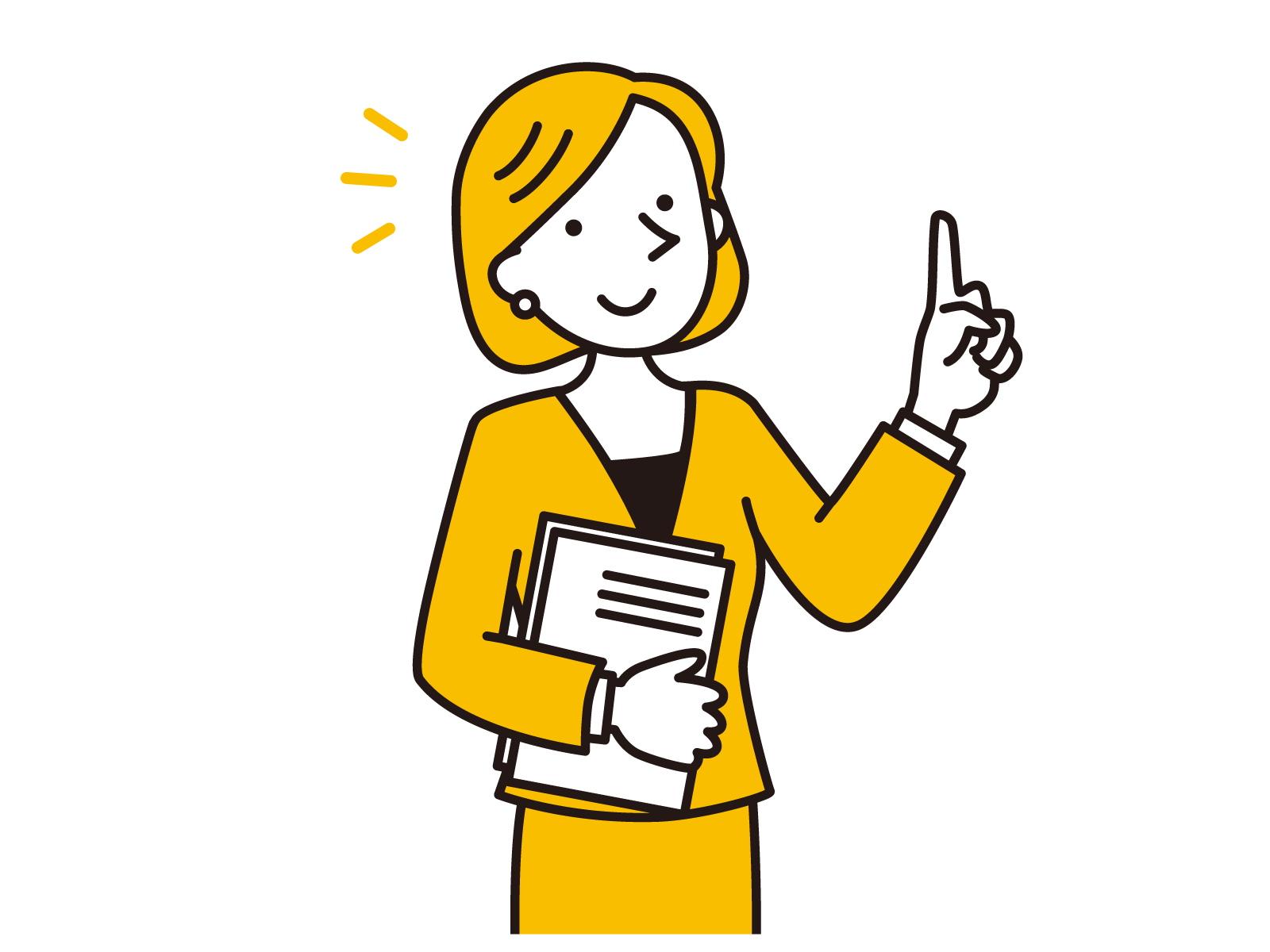
「経審の点数をより良くしたい…!」
「経審の点数を最適化して公共工事をより良い条件で受注したい…!」
無料ダウンロード 経審の見かたのポイントはこちらからダウンロードいただけます。
みそら では、結果通知書の点数だけでなく、改善点についても専門的なアドバイスを提供しています。評価点数の向上が目指せるだけでなく、将来的な業務の効率化や成長にもつながります。まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
\まずはお気軽に無料相談をご利用ください/
無料で経審結果通知書を診断し、「問題点」や「改善が必要な取り組み」をアドバイスします。経営事項審査へのお悩みにも解決策をご提案いたします。
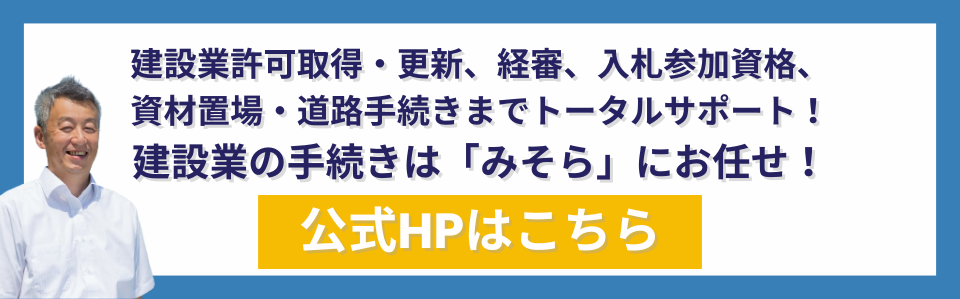
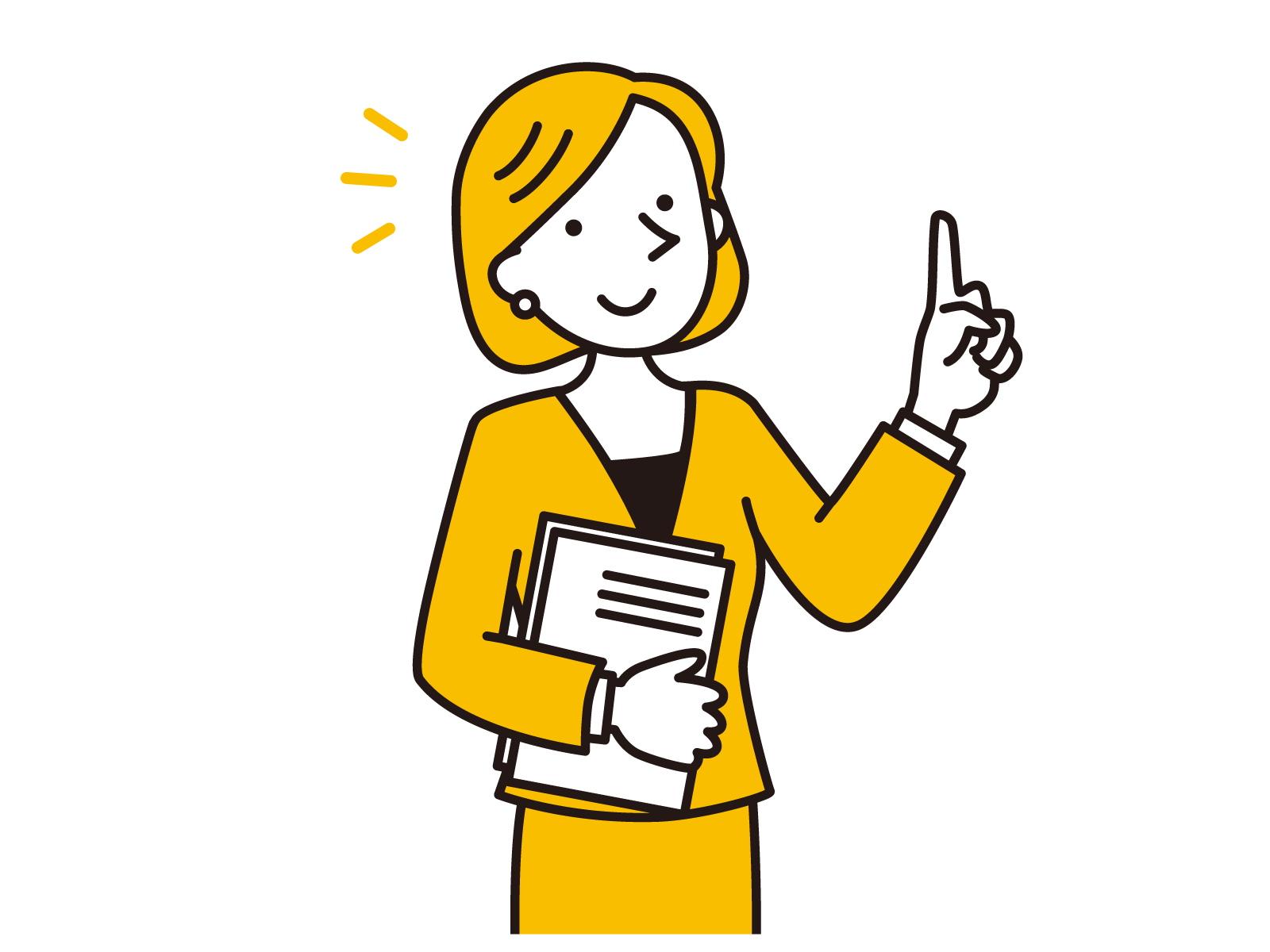
「経審の点数をより良くしたい…!」
「経審の点数を最適化して公共工事をより良い条件で受注したい…!」
無料ダウンロード 経審の見かたのポイントはこちらからダウンロードいただけます。