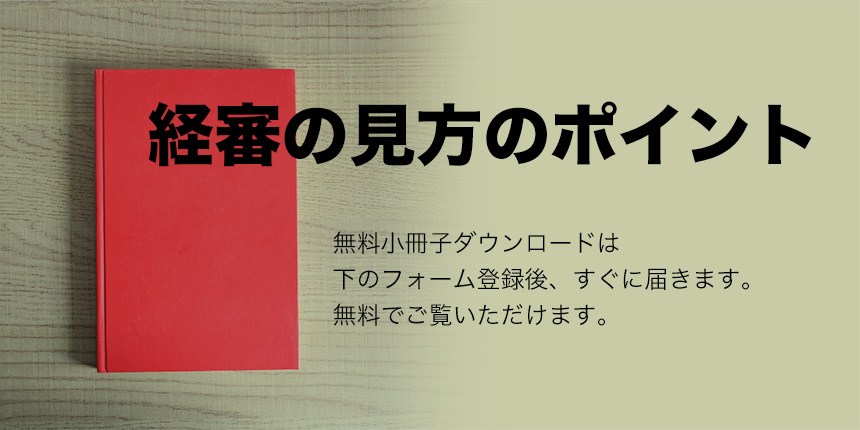「こういう契約書なんですけど、印紙はいくらのものを貼ればいいですか?」と、お客様からよくご質問をいただきます。今回は、この印紙代と建設業の方々にかかわるコンプライアンスについてご案内をしていきます。
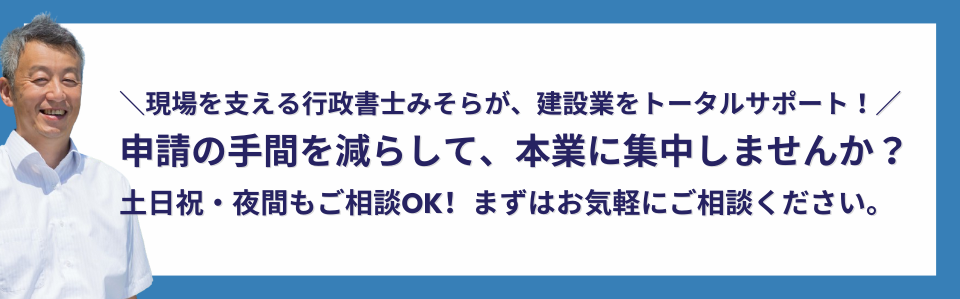

印紙代と軽減措置について
印紙代は誰が負担するのか
過怠税とは?
請負契約書の作成義務について
著しく短い工期の禁止とは
下請け代金の適正な支払いについて
印紙代については、国税庁のホームページに掲載されている最新の「印紙税額一覧表」を確認するのが最も確実です。
建設工事の請負契約書は「2号文書」に該当し、請負金額によって印紙税の金額が変わります。また、平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成される契約書については軽減措置が適用されますので、実際の印紙代は一覧表でご確認ください。
印紙代と軽減措置について
軽減措置の対象となる契約書は「請負に関する契約書(建設工事の請負にかかる契約に基づき作成されたものに限られます。)」のうち、記載金額が100万円を超えるもので「平成26年4月1日から令和9年3月31日」までの間に作成されるものになります。これらの契約書に該当するものであれば、建設請負の当初に作成される契約書のほか、工事金額の変更や工事請負内容の追加等の際に作成される変更契約書や補充契約書等についても軽減措置の対象になります。
請負契約とは
請負契約とは、仕事を依頼する「注文者」と、その仕事を完了させる「請負人」との間で結ばれる契約です。注文者が請負人に対し、仕事を完了させることを約束し、その成果に対して報酬を支払います。
この請負契約には、建設工事などの「形のある仕事」だけでなく、警備や清掃、機械のメンテナンスといった「形のないサービス提供」も含まれます。
請負に関する契約書とは
工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、請負金額変更契約書などが該当します。
印紙代について
| 契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
| 1万円未満 | 非課税 | — |
| 1万円超え 100万円以下 | 200円 | 200円 |
| 100万円超え 200万円以下 | 400円 | 200円 |
| 200万円超え 300万円以下 | 1千円 | 500円 |
| 300万円超え 500万円以下 | 2千円 | 1千円 |
| 500万円超え1千万円以下 | 1万円 | 5千円 |
| 1千万円超え 5千万円以下 | 2万円 | 1万円 |
| 5千万円超え 1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
| 1億円超え 5億円以下 | 10万円 | 6万円 |
| 5億円超え 10億円以下 | 20万円 | 16万円 |
| 10億円超え 50億円以下 | 40万円 | 32万円 |
| 50億円を超えるもの | 60万円 | 48万円 |
請負契約書のなかで契約書の作成通数を規定していると思います。そちらで定めた通数分だけ同じ印紙代が必要になります。また印紙に押す割り印については当事者の双方がしなければならない、という決まりはありません。2度と使えなくするための消印ですので、契約の片方でもよいですし、印鑑でなくてもペンで印をするだけでも構いません。なお、工事注文書と請書の場合には、請書のほうにだけ印紙を貼ります。請書も上記の金額をもとにしてください。
印紙税はどちらが負担するのでしょうか?
印紙税法第3条では、印紙税の納税義務者は課税文書の作成者となっているため、契約書を作成した側が負担することになります。 ただし共同で作成した場合は双方が印紙税を納める義務がある、と定められています。一般的に契約書は2通作成し、お互いが1通ずつ保管するため、双方がそれぞれに貼り付ける印紙代を負担するケースが多いです。協議の上決定をするようにしましょう。
過怠税とは?
印紙を貼らなければならない「注文請書」や「工事請負契約書」などの書面に印紙を貼り忘れてしまうと過怠税が徴収されてしまいます。過怠税の額は、納付しなかった印紙税の額に加えてその2倍に相当する金額(納付すべき金額の3倍)となります。
しかし、貼り忘れに気づいて自ら申し出た場合は納付すべき印紙税の1.1倍に軽減されます。貼り忘れがないか確認すること、そしてもし、貼り忘れていることに気づいたら申し出るようにしましょう。
関連記事
建設業許可の証紙代 一本化したほうがお得?
建設業者としての帳簿の備え付け義務
請負契約書の作成はなぜ義務なのでしょうか?
工事請負契約書は、工事の発注者と受注者が、工事の内容や金額、工期などの条件を明確にするために取り交わす契約書です。書面で契約内容を明らかにしておくことで、後のトラブルや誤解を防ぐことが目的です。契約を結ぶ際には、重要な事項を明示した適正な契約書を作成し、署名または記名押印のうえ、双方で交付します。契約書には、次の内容を必ず記載する必要があります。
【1】工事内容
【2】請負代金の額
【3】工事の着手時期および完成時期
【4】工事を行わない日や時間帯を定める場合はその内容
【5】前払金や出来形部分払いの支払い時期・方法
【6】設計変更や工期変更、中止などがあった場合の取り扱い
【7】天災等の不可抗力による工期変更や損害負担の定め
【8】価格変動などによる請負代金や内容の変更
【9】第三者への損害発生時の賠償金の負担
【10】注文者が資材を提供・機械を貸与する場合の内容・方法
【11】工事完成確認のための検査時期・方法・引渡し時期
【12】完成後の請負代金の支払い時期・方法
【13】契約内容に適合しない場合の責任や保証に関する定め
【14】債務不履行時の遅延利息・違約金など
【15】契約に関する紛争の解決方法
また、建設リサイクル法の対象となる工事では、次の4項目を追加で書面に記載する必要があります。
【1】分別解体の方法
【2】解体工事に要する費用
【3】再資源化施設の名称と所在地
【4】再資源化等に要する費用
契約の締結は、公共・民間を問わず、次のいずれかの書面によって行われます。
【1】請負契約書
【2】注文書・請書 + 基本契約書
【3】注文書・請書 + 基本契約約款
著しく短い工期の禁止について
建設業における長時間労働をなくすためには、まず「適正な工期の設定」が欠かせません。建設工事の注文者は、工事を行うのに通常必要とされる期間よりも「著しく短い工期」で契約を結ぶことが、法律で禁止されています。短い工期での契約は、結果として現場の長時間労働を引き起こすことが多く、その是正が大きな課題となっています。令和6年4月からは、建設業にも「時間外労働の上限規制」が適用され、上限を超える残業は労働基準法違反となります。
※災害時の復旧・復興事業は除かれます(令和6年4月1日~)。
※上限を超える時間外労働を前提にした工期設定は、たとえ元請・下請間で合意があっても「著しく短い工期」とみなされます(令和6年4月1日~)。
著しく短い工期の判断材料について
・見積依頼の際に元請負人が下請負人に示した条件
・締結された請負契約の内容
・下請負人が「著しく短い工期」と認識する考え方
・過去の同種類似工事の実績
・下請負人が元請負人に提出した見積もりの内容
・当該工期を前提として請負契約を締結した事情
・当該工期に関する元請負人の考え方
・賃金台帳、等
著しく短い工期の判断の視点について
・契約で定められた工期が、「工期基準」で示された内容を踏まえておらず、その結果、下請負人が長時間労働など不適正な状態で工事を行うことになっていないか。
・契約工期が、過去に行われた同種・類似工事の工期と比べて短く、そのために下請負人が違法な長時間労働などの不適正な状態で工事を行うことになっていないか。
・契約工期が、下請負人が見積書で示した工期よりも短く設定されており、その結果、下請負人が不適正な労働環境で工事を行うことになっていないか。
工期の変更が必要となる場合にも適用されます
「著しく短い工期」の禁止は、当初の契約締結後、当初の契約どおり工事が進行しなかったり、工事内容に変更が生じた際、工期を変更するために変更契約を締結する場合についても適用されます。
著しく短い工期の禁止に違反した場合の措置について
国土交通大臣等は、著しく短い工期で締結をした発注者に対して、勧告を行うことができ、従わない場合にはその旨を公表することができます。建設工事の注文者が建設業者である場合は、勧告や指示処分を行います。
下請け代金の適正な支払いについて
下請代金の支払いが遅れたり不適切に行われたりすると、下請負人の経営が不安定になるだけでなく、結果として手抜き工事や労災事故などを引き起こすおそれがあります。そのため建設業法では、工事の適正な施工と下請負人の利益保護のため、下請代金の支払いに関するルールを定めています。
できるだけ早い支払いを
注文者から出来高払いや完成払いを受けた場合は、その対象となる工事を施工した下請負人に対して、1か月以内、できる限り短い期間で相当額を支払わなければなりません。
労務費は現金払いを基本に
労務費にあたる部分は、現金での支払いに配慮しましょう。手形で支払う場合も、120日以内の短い期間で設定する必要があります。
前払金を受け取ったときは下請へも配慮を
発注者から前払金を受けた場合は、工事着手に必要な資材購入費や人件費などを下請負人にも前払金として支払うよう努めなければなりません。
完成検査は20日以内に
下請負人から「工事が完成しました」との通知を受けた日から20日以内に検査を行う必要があります。完成後、下請負人が引き渡しを申し出た場合は、速やかに受け取りましょう。
口頭でも構いませんが、後日のトラブル防止のため書面でのやりとりが望ましいです。
特定建設業者は50日以内の支払い義務
特定建設業者が下請負人(資本金4,000万円未満の一般建設業者など)から工事の引き渡しを受けた場合、申出日から50日以内に代金を支払う必要があります。安全衛生費や廃棄物処理費などを下請代金から差し引く場合は、見積書や契約書に明示しておきましょう。
※特定建設業者は、上記【1】と【5】の両方の義務を負います。したがって、出来高払いや完成払いを受けた日から1か月以内、または引き渡しの申出日から50日以内のいずれか早い方で支払う必要があります。
関連記事
建設業のコンプライアンスについて
建設業許可について
建設工事を請け負う建設業の方は「建設工事の種類に対応した建設業許可」が必要です。ただし、軽微な建設工事のみを請け負う場合は建設業許可は必要ありません。
関連記事 建設業許可についての詳しい解説はこちら
建設業許可が必要ない「軽微な工事」について
建築一式工事の場合
下記の①②いずれかに該当する建設工事
①工事1件の請負代金の額※が1,500万円未満の建設工事
②延べ面積が、150㎡(45.38坪)未満の木造住宅工事
建築一式工事以外の場合
工事1件の請負代金額※が、500万円未満の建設工事
※「請負金額の額」とは、消費税及び地方消費税相当額を含んだ金額(以下「税込み」)をいいます。
一般建設業許可が必要な工事
原則
一件の請負契約金額が500万円以上となる工事
例外
500万円以上でも、元請で延べ床面積150㎡未満の木造住宅または請負金額が1,500万円未満の新築または増築工事(建築一式工事)は不要
特定建設業許可が必要な工事
発注者から直接請け負う1件の工事について、その工事の全部又は一部を下請代金の合計額が税込み5,000万円以上(建築一式工事の場合は税込み8,000万円以上)となる下請契約を締結して施工しようとする場合に必要となります。
注意点
・下請契約が複数ある場合は、その合計額で判断します。
・元請負人が提供する材料や機械等の価格は、下請代金に含みません。
\まずはお気軽に無料相談をご利用ください/
無料で経審結果通知書を診断し、「問題点」や「改善が必要な取り組み」をアドバイスします。経営事項審査へのお悩みにも解決策をご提案いたします。
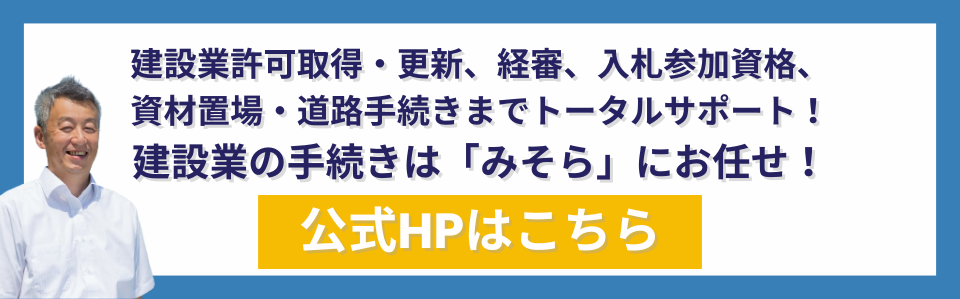
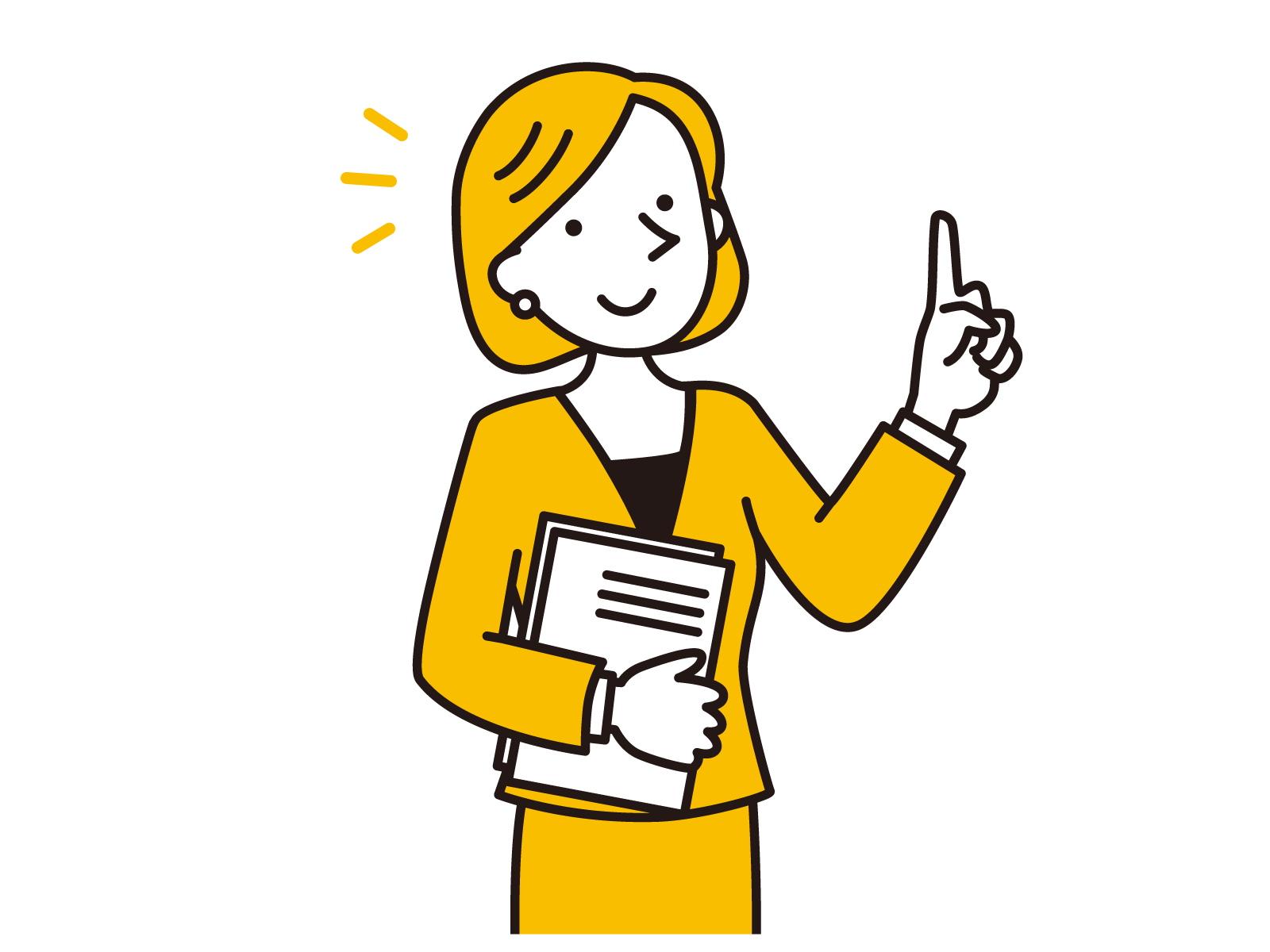
「経審の点数をより良くしたい…!」
「経審の点数を最適化して公共工事をより良い条件で受注したい…!」
無料ダウンロード 経審の見かたのポイントはこちらからダウンロードいただけます。



 www.misora-kensetsukyoka.com
www.misora-kensetsukyoka.com